“老い” と 向き合ってみる
9月に入った。夏という季節と秋が同居する月。
今年も齢を重ねることができた。独りで生きてきたわけではない。多くのひとたち、物事に感謝すべき節目。
そして敬老の日が訪れた。
「お祖父ちゃんやお祖母ちゃんに何か贈り物を!」と思いを巡らせたあの頃はすでに遠い昔である。
いつの間にか、そして当たり前のこととして老いた自分がいる。
その「敬老の日」であるが、この時期になるとお決まりのようなニュースが流れる。
例えば今年でいうならば「100歳以上の高齢者が9万9000人超に…」「長生きの秘訣はくよくよしないこと」。
長寿化の証として、高齢者人口の増加記録が更新したことを告げている。
高齢者としての割合はやはり女性の方が高い。この男女比という比較の仕方に多くの人は違和感を覚えないであろう。だが、仮に100年後・・、その性差表現は変化しているかも知れない。
以前、「理科の時間 人類/生物1」で老化について学んだ。
更に今回は、社会的接点の中で老いることをその当事者のひとりとして身勝手にかつ敢えて無責任に語ってみたい。
改めて、稲垣栄洋氏著作「生き物が老いるということ」のページをめくってみた。
まず生物学的大原則をいうならば人類は、例えば100歳まで生き長らえるようなプログラムで設計されているわけではないということ。当然個体差はあるものの凡そ50年くらいの生涯の想定ということらしい。
人生100年時代とはよく言ったものである。あたかも長生きが当たり前でそれが幸せなことだと決めつけている感じだが、冷静に捉えなおしてみると何となく腑に落ちないのだ。強健ではない自分のひがみでもなく。
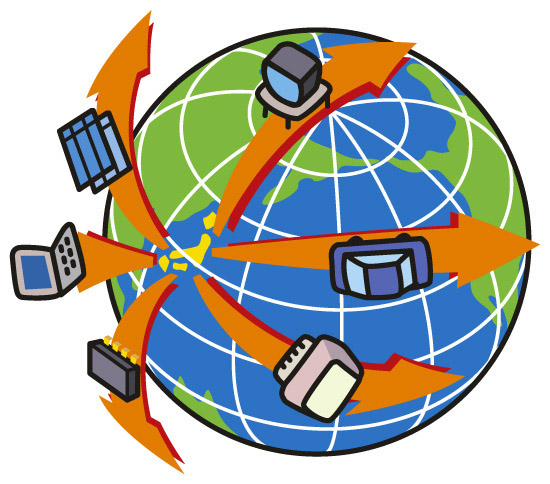
一方で人類は脳の発達によって、その高度な知能を知恵として活用し、様々な経験を繰り返しながら進化発展に繋げてきた。その発展の1つが長く生き続けることを可能とする環境の獲得であり、同時にそれは老いることを可能にしたことと結び付いている。
念を押すような言い方だが、「今のところ」プログラムの制限が解除された、など細胞学において「長寿につながる自然発生的な身体の進化」、その立証はないと思われる。あくまでも医療技術の発展など生き長らえる為の周辺環境が進歩したということである。
この様な論点でしばしば直面する視点がある。それは生物としての見解と社会的な生活者としての見解である。
生物として重要なことは、次の世代に種を残すことである。そして、次の世代を残してしまえば、その役割を終える。仮に100歳を長寿の極みとしても、100年という時間が人類の生存には必要だと言い切れるものではない。
一方で社会的な組織構造を築いていった生活者は、やがて寿命自体も長らえることを可能とする環境をつくり出した。だが共同体として、継続性のある組織的かつ文化的生活の維持を構築しておきながら、その社会的状態を否認するような逆行の歩みを始めている様な気がしてならない。生命とは?寿命とは何だろうか?ちょうどいい塩梅という最期の時は社会的生活者としては見出しづらいのであろう。細胞の分裂回数の制限のように均一に仕組まれるような着地点は無いに等しい。
後世への伝道者たる年配者の存在価値は既に揺らぎつつある。80年から90年そして100年という時間が与えられようとしている中で年配者は何の役割を担えば良いのであろうか?人間が自ら創り出す家族を含めた社会的組織の在り方の変化を一層不安視せざるを得ない。ましてやダイバーシティの中で封印されたような男性性を有するおじいさん達を単体で見つめ直してみると、終末に差し掛かったその男たちの生活的不都合と不具合ははかり知れないと感じるばかりである。
本来、人類は弱い生き物で群れを作り年寄りの「経験と知恵」を活用しながら生き残ってきた。種の存続として、重要な役割を長生きした老年者が担っていたのである。アフリカでは「老人が一人死ぬということは、図書館が一つなくなるようなものだ」と言われてきた。そんな価値観が存在していた事実。今となっては、人間=熟達者たちが有した経験と知恵を披露し活用する機会が既にデジタルデバイスに変わりつつある。
「Artificial Intelligence」、AIといえば聞こえは良いのだが、血がかよっていないものにどこまでどの様な価値視点で頼るのか?と言いたくなってしまう自分がいる。ただこれからの次世代の老人たちは巧みにAIを操っている、そんな頭脳世代になっていることを臨まないといけないのであろう。
いまこの時、純粋なる自然の摂理に逆らってまで人間は何を求めて「老いる」という生物学的には余剰ともいえる時間を獲得したのであろうか?言い方を変えよう。いまの社会において、この老いること、長寿であることの反映としてもたらしていることは何だろうか。そこに笑顔があるとしたら、それはどの様な笑顔なのだろうか?
基本的な考え方としては、老いつつも長寿へと向かう局面を猛進できていることは喜ばしいことであるはずだが・・。
ただ、そこに留まることなく、不老不死などの人類の人間的な欲望は消えることはない。
何も古きことの良さを絶対的価値だというつもりはない。目まぐるしく多くのことが変化する現代、学んだ経験も時代とともに意味をなさなくなる事実と現実。真夜中であってもAIに聞けば大概のことは答えてくれる。
この進化の中で発生する社会的変化が自らの老化と老後というタイミングに隣合わせで存在してしまった。進化は決してマイナスの変化ではない。ただ自分の考え方や想定がどうしても見通せず定まらない、そんな居心地の悪さが伴ってしまっている自分であり、世のおじさんたちではないだろうか。それがアナログな世界を経てから、この老後というデジタルな世界に突入した者の定めなのかも知れないが。
今どきのおじさんの老後戦略

と、それっぽい小見出しを付けてみたのだが。50歳であれ60や70歳であっても同じように今という時間が存在し、それぞれが何らかの先々を控えている。生きることが継続している限り良かれ悪しかれ様々な相応の生活が訪れる。
人生の集大成の在り方は基本、自己責任である、と自分は考える。最期の最期は悪あがきすら不可能となる。長生きをすればする程、老後という時間が長ければ長い程、その未知なる将来は予測不能な数々の賽の目として並び立つ。
よく言われる言葉であるが、正直申し上げて、「老後を豊かに生きる!」という意味が掴みづらい。
ただこの書籍の中で改めて合点がいった一節があった。
今の時代の人間どうしの比較ではなく、地球という生命史となると自らのそのちっぽけな存在性も肯定し、オンリーワンという独自性を素直に尊重できる様な気になってくる。
更に「豊かに老いるということ」について言及している。
人の成長をイネの成長に例えて、最後の実りのステージは精神性を高める「心のステージ」だという。次の世代に残すべき「米」とは、お金や名誉ではなく「生き方」「老い方」「死に方」を見せることである、と説いている。
言葉としての理解は容易い。だが、周辺を見回すと自らを含めた特におじさん達においては、どこまでこの考え方に沿った生き方、老い方をしているのかと疑問を抱いてしまう。どのくらいのおじさん達が?とその比率を探ってもしょうがない。ましてやそれを格差社会の歪みとして捉えたくもない。生き方が不器用なおじさんも多い。その現実は理想だけでは語れないと疑心暗鬼になっている自分がいる。
更に難しくとも感銘を受けた一節があった。スイスの心理学者トゥルニエの言葉として紹介されていた。
「人は老いに従うことのみによって、老いを自分のものにすることができる」と。
この言葉に対して、自己流の解釈をしてみた。
「人は老いに従うことのみによって」全てはこの言葉に集約されていると感じた。理解というような大それたことでもなく、感じ方として。この言葉の奥に隠されている価値観は、謙虚さであり潔さ、ある種の諦め、柔軟さ、定め、敢えて付加するのであれば武士道の精神、四字熟語で例えるならば「行雲流水」であろうか。帰結として「老いを自分のものにする」とは老いを楽しむこと、、であって欲しいと切なく思う限りである。
生物学的見地を別とすれば、人間にとってのミッションは生殖に限ったものではない。理由はともかく人間がなすべき役割は老後を含めた膨大な時間の中で成し遂げる可能性を秘めている。それは個々人においても同様である。ただ注意すべきは、特におじさん達においては、「仕事」という最大級のミッションを成し遂げてしまった後の焦燥感の発生は否定できないことであろう。しかし、おじさんはミッションを失って宇宙空間に放たれた宇宙船と同じ運命ではないはずである。それがたとえ寂しく孤独な旅だとしても。
私たちが獲得した「老後の時代」がまさしく人間が手に入れた自由な時間とするならば、その自由を謳歌する気構えさえあれば良いのではないだろうか。広い宇宙空間の中で、たった一人の自分という存在を愉しめばいい。高みを目指さなくても良い。高いのは血圧と尿酸値だけで十分である。考え方はそれぞれだが、老いというただ中での日常生活における主導権は家族ではなく自分でありたいものだ。例え頑固おやじとなじられ様とも。成り行き任せという主体性もある。
重要なのは自分ごととして老いること。いまこの時点から実行できることを積み上げていくだけ。その小さな実行可能なモノゴトを維持し、少しづつでも蓄えられれば己の心は豊かな気分を感じるはずである。
最後にこの一節、出口治明さんの言葉で締め括りたい。
太陽も地球もいつかは死ぬが「人は星のかけらから生まれて、星のかけらに戻る」のである。
「なぞ」があるからこそ人生は美しく、科学を超えた生きる楽しさと美しさがある。
この言葉に出会ってしまったら、全ての論評が不要に感じる程である。
参考書籍
稲垣栄洋(植物学者/静岡大学教授)
著作「生き物が老いるということ」


