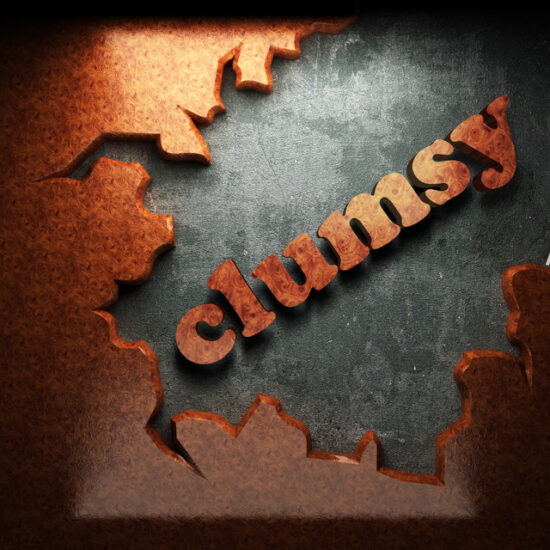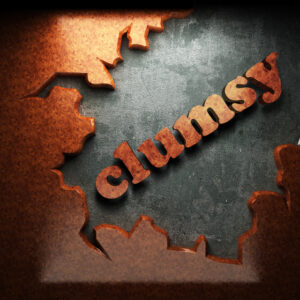ひとり言を無意識にいってしまい「うざい!」と言われてしまうおじさん。ちょっと真面目に呟かさせてください!
自らを確認する意味でも・・
言葉を通じて自らと対峙する機会が必要な気がする。些細なことに目と心を止めてみる。
小さなことの積み重ね。貯金箱が5円玉でいっぱいになる。そんな質素で素朴な幸せ。
寸言集 2025.4.1 ~2025.7

【2025.4.3】深雪桜が咲いた・・
深雪桜であるが、ある盆栽園の棚で5年程前に出会った。桜は枝が枯れやすい。持ち崩して今の形であるが今年は花を付けてくれた。ただ、改めて深雪桜を調べてみたのだが、検索でヒットするのは「霊宝館の醍醐深雪桜」だけでしかもしだれ桜。花色も違う。名前の由来は何だろうか?実は近しき人と同名で・・。

【2025.4.5】「馬酔木(あせび)」が咲いた・・
馬酔木。葉にグラヤノトキシンなどの有毒成分が含まれていて、馬がこの葉を食べると毒にあたり、酔ったようにふらつくようになる、そんな木として命名されたようだ。これも人間の勝手であり植物に罪は無い。情緒ありながら豪華な雰囲気も醸し出していて素敵ではないか!

【2025.4.6】三回忌 總持寺
總持寺(そうじじ)で叔母の三回忌法要がとり行われた。鶴見にある総持寺は、曹洞宗の仏教寺院である。永平寺と並ぶ日本曹洞宗の大本山。1911年に石川県鳳至郡門前町から移転された。何度来ても迷ってしまう広さである。
多くの著名人が眠っている。

【2025.4.7】スミレたち
日本に自生する野生のスミレは約80種、変種などを含めると200を超える品種があるようだ。
この季節、身近なところでスミレの開花が始まった。まずはタチツボスミレ。山間の木陰など比較的日当たりの悪い場所で見かける淡い紫色の花弁と丸い葉が特徴のスミレ。
それとは対象的な路地スミレ?野路スミレ?この辺の違いも微妙だ。こちらは日当たりを好む。名前の由来につながるのか?歩道脇のアスファルトの隙間で力強く咲き誇っている姿をよく見かける。日当たりを優先? 種を飛ばしても地面に無事着地出来なさそうな気がして心配だ。夏場の温度も相当高そうだ。白花も見つけた。それぞれの可憐さがある。道の片隅で力強く咲く、そんな春を象徴するスミレが好きだ。踏まないでね。



【2025.4.12】サクラソウが咲いた。「駅路の鈴」。
サクラソウの歴史は古く江戸時代まで遡る。荒川流域の一帯、下流の戸田ヶ原、浮間ヶ原などは原種の自生地としてかつて有名だった。また「田島ヶ原サクラソウ自生地」は、いまは国の特別天然記念物に指定されている。江戸時代からサクラソウの名勝地として人々に親しまれてきたのだ。江戸の文化の継承。現在栽培されている約300品種は原種から作出されたわけだが、花型と繊細な花色の豊富なバリエーションは多くの人たちの心を魅了する。お江戸日本の伝統的な古典植物である。
今回我が家で咲いたのは「駅路の鈴」。江戸中期に作出された品種。桃色で白覆輪、「目(花の中心部)」は白。咲き方は梅花咲き。この細かな花芸が人々を虜にしていきた。
旗本や御家人などの武士階級は、新花を持ち寄って互いに品評したのである。江戸幕府の崩壊と共にこのブームも衰退に向かったのだが、明治から昭和へと時代が変化していく中でも愛好者は途絶えることなく今に続いている。
この時期、屋根付きの五段構造の展示台に様々な品種を飾り立てるサクラソウ展示会が開催されている。是非ともこの伝統園芸の灯を後世に伝承すべく足を運んでいただきたい。

【2025.415】坪庭の息吹 山吹草と一輪草
狭苦しい敷地。日当たりも今一つなのだがそんなスペースで今年も開花してくれた宿根草の2種。「山吹草と一輪草」。ヤマブキソウは低木のヤマブキに似た山吹色の花を咲かせることからその名がある。ちょっと可哀想な気がするけどよくある話。この鮮やかな山吹色はお見事だ。方やイチリンソウもヤマブキソウと同じく、木陰の草むらや林床で見かける代表的な春の植物。地下茎が這うように伸びて増えていく。最近はヤマブキソウの陣地までその根は及んでいる様で今後が心配。イチリンソウの白い花はまさしく純白。緑と黄と白のコントラストが絶妙である。花の競演の後、晩春ごろから葉が枯れ始めて、初夏には地上部が枯れて、来年の春までを地下部のみで過ごす。
なんか休眠って良いかも!!

【2025.417】坪庭の息吹 シャガ
シャガが咲いた。シャガは和名で「射干」と書く。アヤメ科で学名は「Iris japonica」だが、原産は中国東部~ミャンマーである。
確かにきちんと観察してみると白地に青い斑点が入るこの小さい花の姿、あやめに似ている。
日本各地の低地や人里近くの森林の木陰に見られる常緑多年草。
この奥ゆかしい派手さに心が惹かれる。

【2025.4.20】坪庭の息吹 シラユキゲシ
シラユキゲシ。白雪芥子と書く。名前の通りケシ科のようだが、原産は中国南西部から東部の標高1400~1800mの藪や森林地帯である。
白い花の中心部に黄色の雄しべを纏うその姿はケシの花を感じさせる。こちらも半日陰に生える多年草。下草として大地に支えられながら咲き誇るその花びらは繊細である。所在は地味だが花自体は特にその色調たるや厳しい冬を乗り越えて思いっきり開花する躍動感に満ちた色調だ。早春の花の個性かも知れない。

【2025.4.24】坪庭の息吹 ヤマシャクヤク(山芍薬)
ヤマシャクヤクは山地の林床に生える野生のシャクヤクである。本州、四国、九州および朝鮮半島に分布する。
白い5弁の花で5cmぐらいの大輪、白い花弁に黄色の葯が映えていて優雅さがある。ただ、2~3日で散ってしまう。散るというよりは、落ちると言った方が相応しい表現かも知れない。実は撮影をしていた時に手前の花弁がぽろっと落ちてしまい、そーっと添え直して撮影した。短命花。これを単なる定めとは言いたくない。この潔さこそ、わが郷に通じる神髄と重なる部分を感じる。因みに花後はやがて結実し、その種子は黒く、赤く色づきその色彩はとても美しい。

【2025.5.1】坪庭の息吹 シロヤマブキ
シロヤマブキ(白山吹)が咲いた。一般的な山吹色のヤマブキよりも珍しいので植えてみた。
細かい情報になるが山吹色のヤマブキは花びらが5枚または八重咲きでありヤマブキ属になるが、このシロヤマブキは4弁の白い花を咲かせ、秋に黒く光沢のある実を4個つけるのだが、シロヤマブキ属に分類される。この実であるが地味だけど結構の間、枝先に残っている。それはそれで風情があるけれど・・。ふつう植物は鳥などに食されることによって生息の域を広げていくので人気がないのは美味しくないからであろうか、春先まで残っているのは心配である。
ところでよく似ている樹でヤマブキ属のシロバナヤマブキがあるという。
花びらが5枚で、茶色い実をつける。
それぞれの個性。大切に心得ていたいもである。

【2025.5.4】坪庭の息吹 ホウチャクソウ(宝鐸草 チゴユリ属)
アジア大陸の東端全域に見られ、日本全国に分布。山地や丘陵地の雑木林などの樹間のひらけた場所に群生する。この独特の名前の由来であるが、京都の東寺の五重塔に施された宝鐸によるという。花が垂れ下がって咲く形状が似ているのだ。
宿根草で冬、枯れていた地上部が春になって芽吹いてこの可愛らしい花を咲かせてくれると妙にほっこりした気分にさせてくれる。
斑入りがその個性を引き立ててくれる。地味だが白と緑のグラデーションが美しい春の山野草である。

【2025.5.15】坪庭の神秘 キンラン
キンランはラン科キンラン属の多年草であり、山や丘陵の林の中に生えるランの一種である。2年ぐらい前に叔父の家の裏庭に生えていた株を譲り受け、坪庭の片隅で栽培を始めた。高さ20cmぐらいであろうか、昨年より勢いが落ちている。こちらはキンランという名の通り、黄色い花をつけるランである。因みに白花のギンランも存在し、昨年同じく地植えにしたのだが発芽もしなかった。
このキンラン、花は全開せず半開き状態のままなのだが、その控えめなところが魅力である。
キンラン、そしてギンランも人工での栽培が極めて難しいといわれている。その理由は極めて学術的で繊細な生態系のあり方をその根拠とするものである。単純な表現をすれば、生育に必要な栄養分を菌根菌に依存しているということであり、菌類との共生関係が乱された場合、直ぐに枯れることはないとしても長期的に生育することは困難になってしまう。
一昨年からこのキンランの傍にコナラを植え込んでみた。そして昆虫用の発酵マットの菌糸を側に埋め込んでみた。安易といえばその通りであるが来年も芽吹いて欲しい一心である。いずれにせよこのキンラン、ギンランの繫栄は自然がつくり出す妙技によって成り立っており、里山の自然環境の中での立ち姿が美しさの極みのように思える。
菌根共生するラン科植物は多い。まさしくこの共生という関係性は、人間が頭脳を屈指しながら希求し、作出する手段とはほど遠い従順なるバランス感覚である。そもそも人間もこの地球における自然界の共生者の一員であるはずだが・・。 1997年に絶滅危惧II類 (VU)に登録されている。


【2025.6.6】 ビオトープ池の閃光
小さなビオトープの池でハナショウブが咲いた。
紫色の花びら、優美で滑らかな形状が特徴。
この鮮やかさは梅雨を迎え入れるこの時期に元気を与えてくれる明るさがある。
花の説明はともかく、
ハナショウブの花言葉は「優雅」「心意気」「優しい心」「うれしい知らせ」。 ますます心を躍らせてくれる花。

【2025.6.14】 控えめな彩 ヤマアジサイが咲いた
ヤマアジサイが静かに開花した。アジサイ科アジサイ属の1種。
山中の比較的湿潤な場所にみられる。
落葉広葉樹の低木で枝は細くガクアジサイと比べて小ぶりで弱々しく繊細な印象を受ける。
花の色は多様であり、何といっても艶のない山野草にも通じるしおらしい葉の展開に大和の雅な世界を感じる。
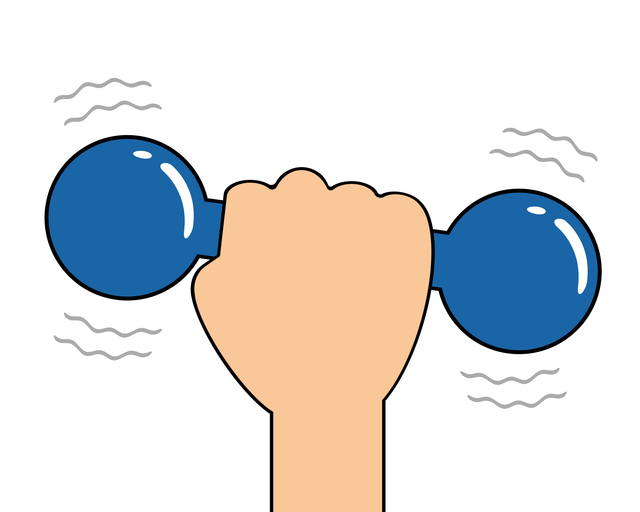
【2025.7.29】自分にとって必要なエネルギーとは
最近いただいた言葉の中に〜食べ物〜と題する一文があった。
「食べ物はエネルギーです。自分にとって必要な分のエネルギーを摂れば良いのです・・」と。
「必要な分」と「必要なエネルギー」とは何だろう?と派生させて考えてみた。
身体を維持する上で「食べ物」は、欠かせない。腹八分目という言葉があるように程々に摂取することが望ましい。ただそれ以上に重要なことがある。心を満たすこと。その向こう側にはきっと誰かがいるはず。感謝。感謝という心の備えは、最大のエネルギー供給源である。