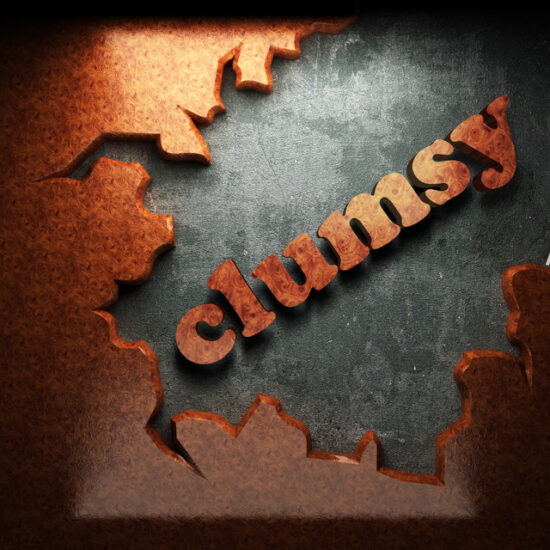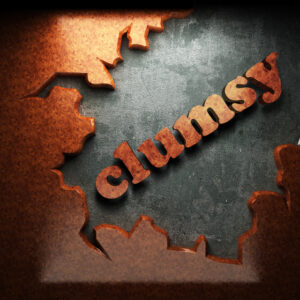ひとり言を無意識にいってしまい「うざい!」と言われてしまうおじさん。ちょっと真面目に呟かさせてください!
自らを確認する意味でも・・
言葉を通じて自らと対峙する機会が必要な気がする。些細なことに目と心を止めてみる。
小さなことの積み重ね。貯金箱が5円玉でいっぱいになる。そんな質素で素朴な幸せ。

【2025.8.16】 都会の花火 hanabi
お盆明けの土曜日、外苑前のシェアオフィスのフロアから打ち上げ花火を鑑賞した。約1時間。様々な色や姿の花模様が照明の消されたグラウンドから立ち上がった。3階のガラス越しのその特設観覧席は贅沢な空間である。
飲食が用意され汗をかくことなく眺めることができる。
子供の頃、汗をかきながら自転車をこいで多摩川の花火大会に行った。
砂ぼこりに紛れながら、火薬の匂いと音を身体で感じた。
いまとなっては、そんな経験の方が楽しかったし、夏の思い出としては適している気がしてならない。

【2025.9.4】 忘れてはならないこと
また1つじじいになった。
1962年。だいぶ前の時代のような気がする。
必ず訪れる日。しかし限りあるこの日。
社員の皆様からの花束。
感謝・・限りなく尽きるものではない。


【2025.9.8】 エンセファラトス・ホリダスがフラッシュした!!
本日、素敵な出来事が幾つかあった。
その1つがエンセファラトス・ホリダスのフラッシュ(新葉の展開)である。
マニアの間では超有名で憧れの的、南アフリカ原産のブルーのソテツ、姫鬼蘇鉄である。
立体的で鋭い棘を持った葉、優美に湾曲した枝ぶりが特徴的でその魅力を語ったらキリがない。
日光を好み、強い光にあたった葉はよりシルバーブルーになる。
何ともいえない葉色。
ワシントン条約Ⅰ類の貴重種に登録されている。
責任と愛情は隣り合わせ。

【2025.9.17】 夏の昼下がりのうたげ。サルスベリの赤い情熱。
黒いシックな葉はカラス葉と称される。そのしっとりとした黒い艶葉と赤い花のコントラストは、情熱的な夏の彩りである。
和名「サルスベリ」はサルも滑り落ちるほど樹皮がなめらかであることに由来する。そして別名の「百日紅」は花期が長いことから付けられという。
伸びた新梢の先につく丸い花芽は愉快な佇まい。楽しい夏の象徴である。

【2025.9.21】 初秋の収穫 「ミョウガとシソ」
①みょうが ショウガ科ショウガ属の多年草
収穫されたのはみょうがの地下茎から出る花穂「花みょうが」とも呼ばれているもの。みょうがは8月頃に収穫される「夏みょうが」と、この時期に収穫される「秋みょうが」があるという。注目すべき点はその成分と効果。
α-ピネン(リラックス効果・発汗・血行促進・食欲増進)、カンフェン(抗菌・抗炎症)、ミョウガジアール(辛味成分/抗菌や解毒)、アントシアニン(赤い色素の成分/ポリフェノールの一種。生活習慣病や老化の予防~抗酸化作用)、カリウム(五大栄養素「ミネラル」の一種/体内の余分な塩分を排出し、むくみや血圧の上昇を抑える)。その他、ビタミンB1、ビタミンC、カルシウム、葉酸、鉄、マグネシウムなど多くの栄養成分が含まれている。
②同時にこの時期の救世主?「しそ(紫蘇)」。
こちらも栄養成分が豊富に含まれている。「しそ」はミネラル分が多く、特にβ-カロテン、ビタミンB2、カルシウムの含有量は、野菜の中でもトップクラス。 β-カロテンは、体内でビタミンAに変換され、口や鼻、のどや肺、胃腸などの粘膜を健康に保つ。免疫力の向上にも役立つので、夏バテ対策にも。まだ幼い穂だが、その実は、「紫蘇子(しそし)」という漢方薬の生薬にもなっている薬効の高い食材なのです。まさにこの時期、いや時期を問わず我々にとって最良の食菜。やはり自然と共に生きる、これが正しい判断です。


【2025.9.29】 秋の七草、萩(ハギ)の花。小さな色彩のしらべ。
全国各地の日当たりの良い野山に生える落葉低木のヤマハギ(山萩マメ科)は昔から身近な植物である。画像は江戸絞りという品種でこの変わり花の色彩に魅了された。狭い庭の片隅に植え込んだのだが、枝が繁茂し過ぎてしまい夏場から面倒だなぁ、と思いつつ剪定を繰り返していた。そのおかげ、いや悪影響で花数が少なくなってしまった。 人間の勝手だが、この小さな花に心を寄せられるような余裕を持たないと・・と今更ながら思う自分。
秋の七草はその美しさを鑑賞して楽しむものである。万葉集は植物が多く詠み込まれているが一番多く登場するのが萩である。
剪定し過ぎたお詫び?に万葉人の気分に寄り添ってみたい。
「秋萩の古枝に咲ける花見れば本の心は忘れざりけり」
(凡河内躬恒)
日本的な美意識にたまには触れてみては如何でしょうか。

【2025.10.2】 素敵な器で差し入れ~ 郷の住人から自家製梅干し
子供の頃から親しまれてきた梅干し。祖母の家の縁側で天日干しされていた梅を摘まんだ思い出がある。梅の下処理から始まって、塩漬け、天日干しなど結構手間がかかるみたいである。
そんな身近な梅干しだが、思った以上の効果効能があった。
あの酸っぱい成分のもとであるクエン酸は、疲労回復や食欲増進効果がある。また、カリウム/マグネシウム/カルシウムなどのミネラル類も豊富。例えばカルシウムは、自律神経の働きにも影響を与え神経の興奮を抑える働きがある。
高血圧予防や骨や歯の健康維持にも役立つようだ。皮膚や粘膜の健康を維持したり、免疫力を高める効果、挙げ出したらきりがないほどである。特になるほどね!と説得力があるのは、消化系の話し。梅干しを食べたときに口の中で大量に分泌される唾液には、消化酵素のアミラーゼが含まれていて消化を助ける。同時にそのアミラーゼは、でんぷんを分解、更に体内でブドウ糖にまで分解され、体を動かすエネルギーとして利用されるのだ。
日本人の主食、お米にはでんぷんが豊富に含まれている。そのお伴の1つである梅干しの作用は言うまでもない。このコンビはご飯の消化を助ける意味で理にかなったペアなのである。最近、日の丸弁当は何処に?
最後に吞兵衛の諸氏に2点程。肝臓の機能をサポートし代謝を高めるという朗報。梅に含まれるピクリン酸という有機酸のおかげ。この作用により、梅干しは二日酔い防止の効果が期待できるのだとか。ただ、当たり前の事ではあるが、食べすぎには要注意ということ。言うまでもなくそれなりの塩分量によって、やはり食べ過ぎれば体のむくみや高血圧の原因にもなるわけで。トータルな塩分摂取量で図ってみても梅干しを毎日食べるとしても、目安は1日1粒まで。梅干しは、おいしく健康的な食品ではありますが、何事もほどほどにということで。