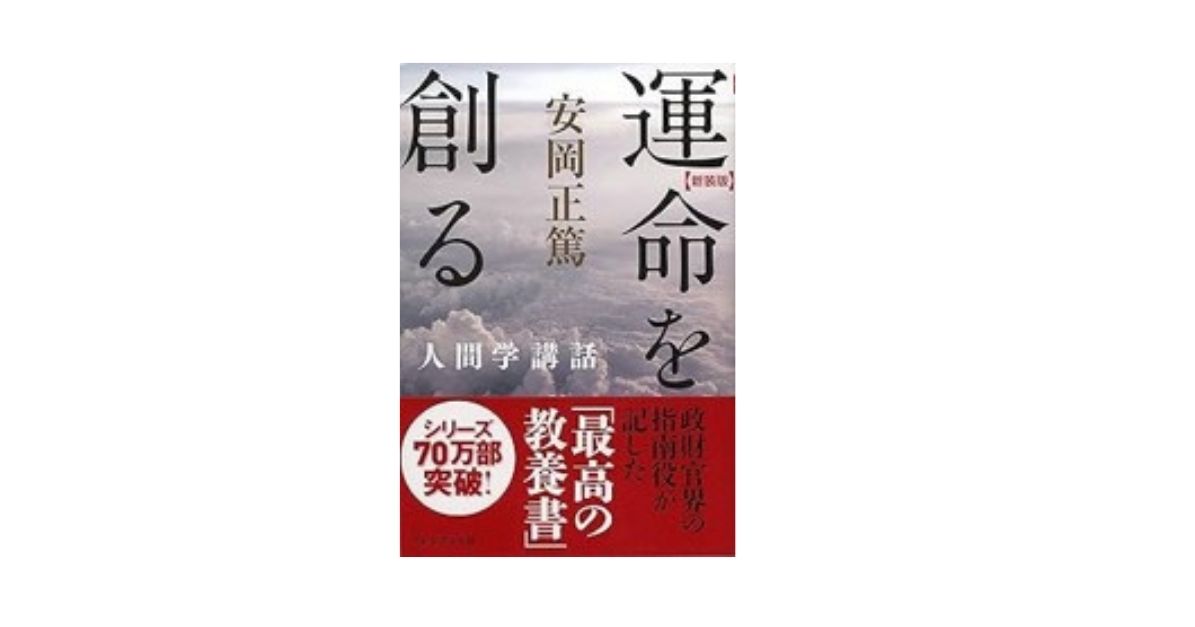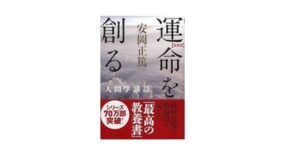「運命を創る」(安岡正篤)人間学講話
発想の柔軟性と謙虚さ
安岡正篤氏をご存じであろうか?1898年〈明治31年〉生まれの日本の易学者、哲学者、思想家。
私塾「金鶏学院」を設立、日本の伝統的な哲学・思想「日本主義」の立場から保守派の長老として戦前から戦後に亘って活躍した人物である。政界や財界を問わず多くの心酔者が存在、彼に指南を仰ぐひとは絶えることはなかった。彼に傾倒する者は今なお変わることなく存在し、自分もその一人である。
今回、彼の著書の中から「運命を創る」、この一冊を手に取ってみた。幾つかのコンテンツの中でふと目に留まった一節があった。
「なぜ「足る」なのか」。
いわゆる「足るを知る」という諺にまつわる話である。この足るを知るという諺としての学びは、これまでは京セラ創業者稲盛和夫氏の経営哲学の書に触れる中での認識が大方であった。
今回、安岡先生の書に目を通している中で、この「足るを知る」という同じ一文に突き当たったのだが、それは愉快な迷路への入り口でもあった。この「足(あし)」という身近な文字が問いかけてくる言葉の意味として新鮮な出会いがあった。経営哲学とはちょっと違った視点での「足るを知る」という言葉の探究も学びの楽しさである。
念のため、「足るを知る」についての定義に触れておきたい。
その由来は、古代中国の書物『老子』(道徳経)の第33章に収められている言葉である。道徳教の記されている「知足者富、強行者有志」という一節。この知足者富の部分が現代語に訳され「足るを知る」ということわざになったとある。
この老子「道徳教」であるが、老子という人物の実在性すら怪しいという説がある。老子は半ば伝説上の人物で、著者が特定できないのである。さらに、その人物が一人で『道徳経』を書いたということ自体が疑わしいとされている。
因みにこれまで語られてきた「老子」についての見解であるが、「老子は、中国春秋時代における哲学者。諸子百家のうちの道家は彼の思想を基礎とし、後に生まれた道教(中国三大宗教(三教)「儒教・仏教・道教」の一つ)は彼を始祖に置く。「老子」の呼び名は「偉大な人物」を意味する尊称と考えられている」とある。
(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)
この「足るを知る」であるが、その解釈など多くの論説が存在する中でちょっと変わった視点でこの言葉を見直す機会を与えてくれたのが安岡先生の「運命を創る」である。その一節を辿っていきたい。
なぜ「足る」なのか
【私中学のときに国語の先生から「楽しい」という言葉の言語学的な話しを聞いた。楽しいということは、子供が母の胎内で「手をかがめているが、その手を伸ばす、すなわち、手伸ばし↓てのし↓たのし、である。縮まっているものを伸ばすという意味である。生命の伸長、これが「楽しい」の語源だという。こういう話を面白いなと感心して聞いたのであります。
それで咄嗟に頭に浮かんで、「それでは先生に質問しますが、『たる』という一言葉はなぜ『手る』と書かないで『足る』と書きますか」と言うと、先生は「理屈を言うな」と言われたので、仕方がないから引き下がったが、私ははなはだ不満であった。「たる」がなぜ「足る」であるか疑問に思ったのでありますが、先生は理屈を言うなと言われた。しかし、これは私の方が正しい。本当の教育者というのは、そんなことは言わないで、「それはいい質問だ、僕は気がつかなかったが、それは面白いから、ひとつ研究しよう」と言ってくだされば、こちらも非常に気合いがかかる。ところが、自分の分からぬことだから理屈を言うなといって、こちらのいうことは聞き入れない。これは人を教える態度でないばかりか、そもそも人生に処する態度ではない。それが純真な青年の気持ちとしては不満でしょうがない。
爾来「たる」は足るであって手るでないということが頭にこびりついて離れない。だんだん自分で学問ができるようになってから、あらゆる漢学の書物を引っばり出して、つまり注釈を調べて、足に関する文字、熟語は調べられるだけ調べてみたけれども、いかなる書物を読んでも、なぜ「たる」は足るで手るでないかということを説明したものがない。もうあきらめていたのであります。
私は小さい頃から漢学を専攻いたしました。世間から言うと俗に漢学者と言われる。だから通俗観念から言うと漢学者は漢学の本を読んでいればいいわけです。通俗観念というものは真に狭いものであります。漢学というともうすでに文科大学に属すると俗人は皆思う。
何が故に「手る」でなくて「足る」でなければならぬかということを明らかにしようと思えば漢学の本を漁って注釈を探っているよりも、手の研究をすればいい、足の研究をすればいい。そうして生理的・病理的・医学的に手と足とどっちが大事かということを研究する。つまり、医学上から手や足を研究すればいい。それが思者の型にはまってしまうと、それに気がつかぬ。医者なんてものは、俺のやることでない、これは医者のやることである、医科大学生のやることであると考えるものだから、生理学・病理学といったようなことはちっとも気がつかない。そのくせ私は医者が好きであります。自分でも医者になろうと思ったことがある。特に医書を読むことが好きで、漢方の医学というものが非常に好きである。医者の友人も非常に多い。私自身、小遣いを倹約して幾人も医学生を育てました。それくらいですから、自分もやればやれるのに気がつかなかった。
私は、その半面、専門違いのいろいろの連中を集めてよく会をやっておったのでありますが、ある晩、会でひょっとその話をした時に、 一人の医学者が卓を叩いて感心をした。「それは面白い、いや実に文字というものはえらいものだ。昔の人は偉いなあ」と言って非常に感心をしている。のみならず彼は、「今夜は革命的な一晩だ」と言って一人悦に入る。「一人感心しておらずに説明をしてほしい。僕は長い間そのことで苦労してきた」と言うと、「いや、手と足とを生理学的・病理学的・解剖学的に研究すると、それは問題なく足の方が大事です。足によって全身の問題は解決することができます」と言う。それから縷々(るる)長広舌を承って、私の多年の疑問が初めて解けた。「たる」は「手る」でなくて「足る」でなくてはならぬということが初めて医者によって判明した。
〈編集部注・著者は、別個の講演で「足る」についての医学的説明を以下のように述べている〉
(その医者によると)人間の体で一番苦労しているのは足である。人間は寝ても覚めても大気の圧力、地球の引力、重力の圧力を受けている。何をしても、この支配から脱することはできない これに順応する一番楽な姿勢は横になることである。故に、匍匐する動物は一番合理的な体勢をとっている。人間は立ち上がって前足を手にしたことから発達したのである。そうすることにより頭が発達したので、匍匐していると頭は無になってしまう。ですから神経衰弱や胃下垂になっている人など、四つ這いになって歩くと治ってしまう。医者では、患者の体力によって一定時間這わせる運動をさせるところがあります。私自身も御殿場におった時、やったことがあります。これをやると物を考えようとしても考えられなくなり、非常に腹がすくから、胃病など治ってしまう。実によい運動です。文明から原始に返るのです。だから禅寺などでは、盛んに雲水や小僧に拭き掃除をさせます。これをしていると、どんなに悩んでいる時でも物を考えない。頭を空つぼにして四足になって働くから、胃腸は非常によくなる、だから健康にはよいのです。
ところが、立ってしまうと、脊椎という積み重ね方式のひょろ長い、あやふやな柱、それを腰で受けて、その下に二本棒を立てて倒れないようにしているので、実に不自然です。そして曲がったり脱臼したり、いろいろと障害を起こすのです。しかも腰、脊椎は非常に重要です。これから神経、血管、淋巴腺などが全身に分布しているのですから、異常を起こすと体内は色々と変化を起こします。
肝腎要の要は腰である。 (肝腎は肝臓と腎臓)。昔の人が「腰抜け」と言ったのは名言であります。大体の人間は二十歳にもなると多少「腰抜け」です。三十、四十になると「大腰抜け」です。肩が凝るとか、胃腸が悪いとか、これは腰に異常があるためです。
さらに悪いのは足である。足は心臓から出た血液が、そこへ降りてくることはできるが、それを順調に上に上げるためには、あらゆる努力を払っている。足の機能が完全になれば、ほとんど言うことはないそうです。健康である、すなわち「足る」である。手など問題ではない 病気などしたりすると、まず足が駄目になる。フラフラする。足腰が定まらないということが、 一番精神的にも肉体的にもいけない。そこで足をできるだけ丈夫にする、足の機能を旺盛にする、完全にすることが、我々の終身の健康の必須条件である。だから「たる」という意味に足を用いたのであると。それを聞いて初めて、私の多年の疑間が釈然したのです。その友人にしてみると、「今まで自分は臨床医術の上において足というものを忘れておった。体を治してやろうと思ったら、まず足から治してやらなければならぬことを忘れておった。これから自分は患者を治療する上において偉大なる革命的進歩する示唆を与えられたこの晩は非常に有難い」と喜んだわけです。
私はその時に非常に感じた。学問というものは片輪ではいけない。今までのような専門なんてものに囚われておっては行き詰まりだ。「専門的愚昧」ということがある。専門家になると型が決まって非常に狭くなってしまってしまって、その結果、あることについては深く知っているが、他のことは何にもわからぬということになる。他のことが分からぬだけならいいのだが、他のことが分からぬと専門が行き詰まる。専門になるほど富士山のように裾野が広くなければならぬ。できるだけほかの世界に関心を細やかに持たねばならぬ。我々の様な漢学も生理学も病理学も解剖も電気学も栄養学も何学も必要である。と同時に医者そのものも、そういう漢学の一語の問題が彼の実際の医療の上に大なる変化を与えることになります。これは医者がいくら集まって議論してもそういうことは得られない。】
この「足るを知る」という表現、初めて出会った言葉ではなかったが、その表題に再度引き寄せられた。老子(道徳教)の一節に帰する「足るを知る」という教え。自らが謙虚に学び、わきまえることの意義を諭すことが重要なことは言うまでもない。
いま一度この言葉の原点に触れてみた。自省の意を込めて。ものごとに対する頭の中での理解と実行することの隔たりは一様に存在している。その視点では、人生は同じ一つのことにおいても学び続けるという継続が極めて重要であることに再度心が動かされた(単なる未完成なおじさんなのだが)。
同じ一つの事柄においても学び方の違いが存在し、同時に他者への言葉としての示唆(承前啓後)が発生する。そして学ぶべき事柄自体に予期せぬ広がりとしてワクワクするような感動と共に改めて新鮮な提示してくれた一節。それが他ならないこの人間学講話であった。
時代性や独自性は一つの個性かも知れないが自らの硬直化しつつある脳に刺激を与えてくれたのだ。漢学と医学との接点を文明から原始に返るという表現のもと人間本来の謙虚さとして教示するさま。
そして、匍匐する動物との対峙、人間という種の進化にまでも言及しながら、肝腎要の要は腰であるとした言葉の創造で更なる興味を喚起させる。そして、最終的に足の役割、機能としての働きぶりを拝むのである。足の機能が完全になれば、ほとんど言うことはない、と健康であることを「足る」として結論づける。だいぶ老子からは離れているようにも映るのだが、回顧的な導き方としての安岡哲学は妙に心にフィットするのである。
特に今の時代は、スペシャリスト、専門家の方がもてはやされるのかも知れないし、それが素晴らしいことであることは言うまでもない。ただ、今さらスペシャリストにはなりづらいおじさん達がいる。雑学でも自らの裾野が少しでも広くなるようなそんな学びへの興味関心は持ち続けた方が良いと思う。
<参考書籍>「運命を創る」(安岡正篤) プレジデント社